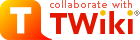
Difference: Feb2022CYRICLOG (12 vs. 13)
Revision 132022-03-02 - AtlasjSilicon
Feb 2022 CYRIC Log pageArticle text. --・KEKで金曜日に撮影された写真には写っている(http://atlaspc5.kek.jp/pub/Main/FEB2022CYRICPhoto2/sampleinbox.jpeg). ただし, この写真が撮られた後で,少なくともプチプチを敷く作業を誰かがしたため,その際にしまい忘れた可能性はゼロではない. --> 石井くんが富士B2を探してくれたが, それっぽいサンプルはなかった.いずれにしても,CYRICには持ってきている可能性が高い. ・サンプル入りボックスを32コース内に持ち込み,テーブル(ビームダンプを置くやつ)でフレームに取り付ける作業をした.後からみてみると,スロット11用アルミフレームはスロット5に書き換えられ,v1.0サンプル用にされていた.サンプルを作っていた時にはできるだけ元のスロット番号を尊重していたため,もしスロット11の3Dセンサーサンプルの取り付け作業をしようとしていたら,その時点で気づく可能性が高い.よって,この時点では存在していなかった可能性が高い. ・全員総動員でターゲット室内と32コース内+通路や待機室などもくまなく探したが見つからなかった. > 液体窒素の補充のために00:35 ~ 01:40:30 で第3ターゲット室にアクセスし,液体窒素の入ったタンクを持ち上げるためにサンプルの入ったアクリルボックスを取り替えようとした際,プチプチの下にスロット11と書かれたpix 3D sensorを発見した.灯台下暗し 見つかってよかった. ・16:00ごろからビーム形状の測定を行なった. --> ケーブルがY軸に引っ掛かっているせいか、照射中央に行こうとするとエラーが出る. ケーブルを修正して復帰. 17:00ごろから20 nAのビームを出してもらい,測定の結果上流でx方向に5.04 mmのシグマ,z方向に4.27 mmのシグマ,下流でx方向に8.72 mm,z方向に6.17 mmのシグマのビームとなっていることがわかった.また,照射中央は上流でx=63.19 mm,z=61.07 mmであり,下流でx=64.3 mm,z=60.48 mmとなった.上流と下流での照射中央の違いは高々1 mmと小さいので,これらの平均を取ったx=63.75 mm,z=60.78 mmを真の照射中央として定義し,XYZリモートコントローラーに入力した.18:00ごろ終了. ・第1計数室の内線:4425 第3ターゲット室:3483 ・20時ごろ モジュール読み出しDAQを開始した. ・20時54分ごろ 照射試験開始に向けてXYZリモートコントローラーの使い方確認.「交換中:ノーターゲット」のバグが再発.照射ボックスを制御する,第3ターゲット室のブレーカーに繋がってる太いシリアルケーブルの,ブレーカーボックスに繋がってる部分をうねうねしてたら治ったのかもしれない.接触の問題である可能性が高いのだろうか. ・v1.1 読み出し試験 -15℃で読み出ししていると,ごくたまにcant establish commnication と言われてスキャンが止まってしまうことがある.-15℃という低温環境下で稼働させたことはないので,もしかしたらそれが原因かもしれない.ターゲット温度を0℃に上げて様子見することにした.-->あんまり温度依存性はなさそう.そのため,-15℃のターゲット温度とし,プログラムの方を書き換えてstd_digitalscanが失敗したときに返すエラーコードでパワーサイクルの可否を判定するようにした.測定が問題なく継続して行えるようになった. Run1:21:06にv1.1の照射開始. 以下,ビーム停止時間帯の記録. ・21:17 15 s ・21:58 15 s ・00:17 15 s ・00:35 アラーム発生 --> いったんビームを止め、リセットをかけて原点復帰. 液体窒素の残りが7 kgぐらいになっていたので, このタイミングで補充をすることにした. --> 1:19終了. ・01:40:30: run 1の残りを再開. ・02:34 15 s ・02:44 15 s ・02.52 9 s 03:20:25,照射終了.液体窒素を補充し,照射ボックス下側のNTC(bottom)で温度コントロールするようにthermo_controll.pyを書き換え, ターゲット温度25℃となるように走らせ直した.しかし,温度が-25℃から上がらず,やはり凍ってしまっている様子.30分で10度程度しか上がらないので, 温度が上がるのを待たずにアクセスすることにした. 04:15,32コースにアクセスして, 以下の作業を行った.
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ・08:27 270 s, Main sensorが設置されているslot2を誤って取り出したまま照射してしまったためビームを止めた. 詳細は後述. ・08:35 16 s ・08:59 14 s ・09:05 13 s Run3, 9:12:01 照射終了.液体窒素を補充 インターバル 15m29s Main sensorの誤照射 slot12の照射前にコントローラーが停止していまい、復帰の際仕様上の問題で空のスロットをTarget setしないとscanが開始しないため、空であると認識していたslot2を取り出して照射を開始していまった。 実際にはslot2にはMain sensorが設置されており、照射開始7:43:10から照射停止8:22:30までの39分間slot12の手前でslot2 のMain sensorが照射されていた。 slot2の厚さは合計でシリコン723umの厚さに相当し、slot2の誤照射によるエネルギーの減衰は1%程度と想定され、これは無視する。 slot2に照射された放射線の量とその面積については現在計算中(AM10:00現在)-> 目標5e15の照射量に近づくよう、Run5では3e15のビームを照射することにした。センサーの端の照射量は3.5e15程度と目標の70%程度の照射量になる見込み。 20サイクルのスキャン時間より短くなってしまうが照射は1600nAのカレントで行う。照射時間は1h31m22sの予定。(11:47現在) Run4:9:27:30 slot4 ITkpix-v1.0 3台の照射開始. 測定時間短縮のためDumpのビームカレントを1600 nAに設定し、照射した. 以下ビーム停止時間のまとめ ・09:35 10 s, 28 s幅のビームの減衰が見られた. サンプルの形状による減衰も考えられたが繰り返さないのでビーム側の問題だと考えられる。 ・09:52 5 s ・10:15 2 s ・11:48 11 s ・12:19 300 s, 12:19:30にコントローラーでエラー発生、再起動して復帰. ・12:44 13 s 12:46:04 Run4 照射終了. スロットを入れ替えRun5開始. インターバル2m26s Run5:12:48:30, slot 2 のMainQuadSensorを照射.Run3での誤照射のためRun5での照射量は3e15. ビームカレント1600 nA. 以下ビーム停止時間のまとめ | |||||||
Comments.%COMME% | ||||||||
View topic | History: r17 < r16 < r15 < r14 | More topic actions...
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback